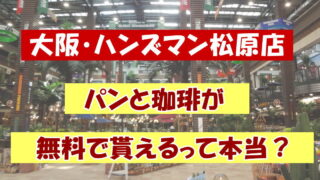 おでかけ情報
おでかけ情報 大阪・ハンズマン松原店|パンと珈琲が無料で貰えるって本当?
ハンズマン松原店(大阪府)では、早朝にパンと珈琲の無料サービスを提供しています♪この記事では、その無料サービスの時間帯やパンの種類、ワゴンの置かれている場所などについて詳しくお伝えしています。
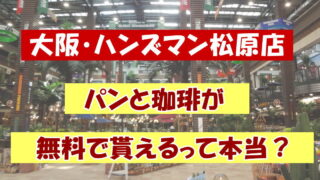 おでかけ情報
おでかけ情報 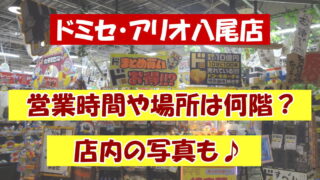 おでかけ情報
おでかけ情報  お役立ち情報
お役立ち情報 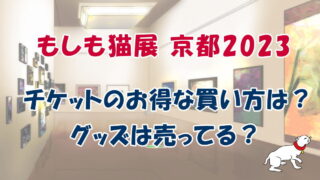 おでかけ情報
おでかけ情報 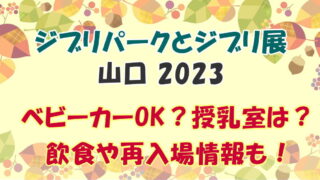 おでかけ情報
おでかけ情報 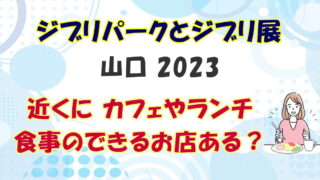 おでかけ情報
おでかけ情報 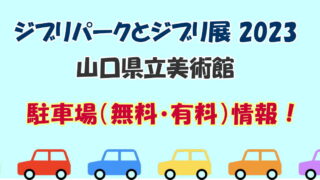 おでかけ情報
おでかけ情報 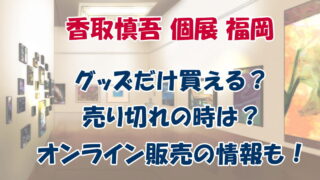 おでかけ情報
おでかけ情報 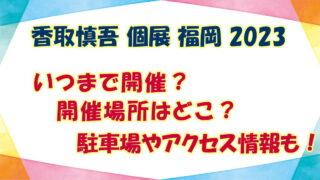 おでかけ情報
おでかけ情報 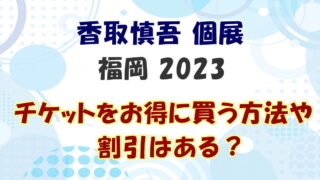 おでかけ情報
おでかけ情報